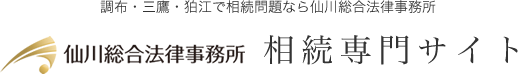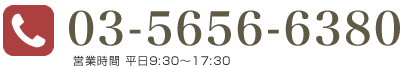相続コラム
遺言書
遺言書
自筆証書遺言をみつけたが、どうしたらよいか~検認について~
2018.08.22
自筆証書遺言をみつけたが、どうしたらよいか~検認について~
1 検認とは
自筆証書遺言書を補完していた人や、発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して調査を求めなければなりません。
これを検認と言います(民法第104条)。
検認は、相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日時点における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手段です。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
2 検認の申立て
検認の申立ては、遺言をした人が亡くなった場所か遺言した人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
検認の申立書には、遺言書を保管もしくは発見した状況を記載し、遺言をした人と相続人全員の戸籍謄本を添えて提出します。
3 検認期日
検認の申立てを行うと、家庭裁判所から、検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。
検認期日には、申立人が、遺言書、印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
申立ての手続きを弁護士に依頼した場合には、申立人と一緒に弁護士も出席します。
申立人が高齢だったりして出席が困難な場合には、弁護士だけの出席でも認められます。
当日は、出席した相続人などの立会いのもと、封筒を開封し、遺言書の形状や記載の方法・内容を調査し、それが遺言をした人の筆跡であるかどうかを立ち会った人に質問して、記録に残します。
なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されています。
4 検認の効力
上記の通り、検認は、その遺言書の有効・無効を決定する手続きではありません。
従って、検認が行われたとしても、遺言書の効力については、後日争うことが可能です。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封しなければならず、勝手に開封したり、検認をせずに遺言書の内容を執行すると、過料の制裁を科されることがありますが、勝手に開封された遺言書もそれだけで無効になるわけではありません。
その他の関連コラム
その他
内縁と相続
2018.08.21
内縁と相続 1 内縁の配偶者に相続権はあるか 法律上、相続権を有する配偶者は、有効な婚姻の届出がなされている夫または妻に限られます。 従って、内縁(いわゆる事実婚)の夫または妻には法定相続分はありません。 ・・・
遺言書
遺言の検認
2020.04.28
検認の意味や手続きについて 1 遺言の検認とは 公正証書による遺言ではない遺言書(自筆証書遺言など)がある場合、相続人の方は、遺言書を発見後遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないことが定・・・
遺言書
遺言書の書き方
2018.08.08
遺言書の書き方 1 遺言書の種類 法的に効力を認められる遺言書には、以下の通りいくつかの種類があります。 ① 自筆証書遺言 一人で作成することが出来る最も簡易な遺言書です。 ② 公正証書遺言 公・・・
遺言書
認知症の症状がみられる場合の遺言書作成
2020.04.01
認知症の症状がみられる場合は遺言書を作成できないか 1 高齢のため認知症の症状がみられるような場合、遺言書を作成することは可能でしょうか。 遺言書を作成するためには、法律上、自ら判断しその意思を表明する能力・・・
遺言書
自筆証書遺言に関する法改正について
2023.04.14
自筆証書遺言に関する法改正について、弁護士が解説します 1 自筆証書遺言の方式緩和~財産目録をパソコン等で作成できるように <以前は全て手書きする必要があった> 旧法では、自筆証書遺言は、財産目録も含め全てを遺言者が手書・・・
遺言書
公正証書遺言の作成方法
2020.02.05
公正証書遺言は作成方法や作成場所、作成の流れなど 1 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、遺言をする方が、公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言の内容を文章にまとめて作成する遺言書です・・・
遺言書
遺言書の探し方
2020.05.15
遺言書があるはずなのに見つからない場合、どうしたらよいか。 1 通常の保管方法 被相続人が、生前、公正証書遺言を作成したと言っていたものの、それがどこにあるかわからない場合、どうしたらよいでしょうか。 公正・・・
遺言書
遺言書のメリット
2018.08.07
遺言書のメリット 1 なぜ遺言書を書くのか 相続に関してトラブルになってしまっている事案の法律相談を受けるなかで、「遺言書があればよかったんですが…。」と言うお話になることが多々あります。 例・・・
その他
遺言執行者の選任と役割
2018.08.23
遺言執行者の選任と役割 1 遺言執行者とは 亡くなった人の遺言が残されていた場合、その遺言の内容を実現するためには、様々な手続きが必要です。 預貯金の解約・分配手続きや、不動産の登記手続き、遺贈や寄附行為な・・・