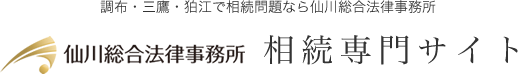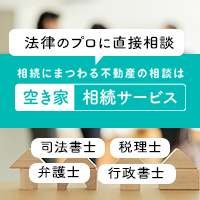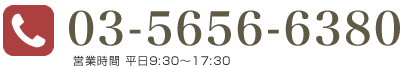相続コラム
その他
その他
相続分の譲渡
2020.05.20
相続分を他の相続人に譲渡する場合、第三者に譲渡する場合について
1 相続分を他の相続人に譲渡する場合
(1)相続分を譲渡するメリット
① 遺産分割協議に参加せずに済む
遺産を取得したくない場合、遺産分割協議に参加したうえで遺産を取得しない合意をすることが可能ですが、相続人が多くいる場合など遺産分割協議が長期化することもあり、全員の協議がまとまるまで、解決することができません。
これに対し、相続分を他の相続人に譲渡する場合、譲渡人と譲受人の二者間の合意だけで成立しますので、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
② 相続放棄の手続が不要
遺産を取得したくない場合、相続放棄の手続をすることが可能ですが、相続放棄は家庭裁判所に必要書類を提出して相続放棄の申述を行わなければなりません。
相続分の譲渡であれば、このような手続を取る必要がありませんので簡便です。
(2)相続分譲渡の方法
相続分を譲渡する方法については特に法律の要件はなく、書面を作成せず口頭で合意するだけでも足ります。
しかし、合意の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するためには、合意の内容を記載した「相続分譲渡証書」を作成したほうが良いです。
2 相続分を第三者に譲渡する場合
(1)具体例
相続分を第三者に譲渡することが有効な具体例としては、以下のようなケースがあります。
【AさんがBさんに借金をしていたところ、Aさんの父Xが亡くなり、Aさんは法定相続人として相続分があるため、この相続分をBさんに譲渡することで借金を清算する場合】
(2)相続分譲渡の方法
相続分を譲渡する方法については特に法律の要件はなく、書面を作成せず口頭で合意するだけでも足ります。
譲渡の有償、無償も問いません。
しかし、合意の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するためには、合意の内容を記載した「相続分譲渡証書」を作成したほうが良いです。
また、相続分譲渡を譲渡人以外の共同相続人に通知する必要があるか否かについては、必要とする説と不要とする説とに分かれています。
念のため、通知をしておくと安心でしょう。通知は譲渡人から行うことになります。
(3)相続分譲渡の効果
譲受人は、譲渡人が有していた包括的持分を取得するので、他の共同相続人に対し遺産分割を請求できます。
反対に、譲渡人は遺産分割請求権を失います。
譲渡人は、遺産分割の協議、調停、審判に参加でき、他の相続人は譲受人を参加させなければなりません。
その他の関連コラム
その他
結婚した娘や養子にいった息子の相続権
2020.09.08
結婚や養子縁組と相続の関係 1 婚姻や普通養子縁組と相続は無関係 結婚して姓が変わった娘や養子にいった息子にも、親の遺産について相続権があるのでしょうか。 このような場合も、もとの親との親子関係が存在するこ・・・
その他
相続 遺産調査の方法~23条照会(弁護士会照会)について
2018.09.04
相続 遺産調査の方法~23条照会(弁護士会照会)について 1 遺産が不明の場合 相続のご相談で多くあるのが、遺産の内容を把握できないという問題です。 例えば、被相続人が生前同居していた家族の一人が事実上の財・・・
その他
相続人に未成年者がいる場合
2020.03.18
特別代理人の選任手続について 1 特別代理人が必要な場合 例えば、父親が死亡して、法定相続人として妻と未成年の子どもがいる場合、遺産分割協議はどのように行えばよいでしょうか。 この場合、妻は子どもの単独親権・・・
その他
農地の相続
2019.12.24
遺産のなかに農地がある場合の相続手続き 1 農地の相続手続き 農地の所有権を移転する場合には、原則として農地法所定の許可が必要です。 また、所有権移転登記を申請する際には許可書を提供しなければなりません。 ・・・
その他
配偶者居住権について
2023.03.28
配偶者居住権について、弁護士が解説します 1 配偶者居住権とは 配偶者居住権とは、夫婦のどちらか一方が亡くなったときに、残された配偶者が、亡くなった配偶者と一緒に住んでいた家に居住を続けることを認めた権利です。 夫婦が一・・・
その他
法定相続情報一覧図とは
2020.10.07
法定相続情報一覧図を活用しましょう 1 法定相続情報一覧図とは 相続の手続きを取る際、相続関係を証明するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を揃える必要があります。 相続手続が複数必要な場合(金融機関・・・
その他
香典や葬儀費用の取扱いについて
2020.08.25
相続において香典や葬儀費用をどのように扱うべきか 1 香典、葬儀費用の法的性質 香典について、法律の規定はありませんが、慣習上喪主へ贈られる贈与と解されています。 葬儀費用についても法律上の規定はなく、必ず・・・
その他
内縁と相続
2018.08.21
内縁と相続 1 内縁の配偶者に相続権はあるか 法律上、相続権を有する配偶者は、有効な婚姻の届出がなされている夫または妻に限られます。 従って、内縁(いわゆる事実婚)の夫または妻には法定相続分はありません。 ・・・
その他
遺言執行者の解任・辞任
2019.10.18
遺言執行者の解任・辞任 1 遺言執行者の解任 遺言執行者がその任務を適切に行わない場合、利害関係人は家庭裁判所に対し、遺言執行者の解任を請求することができます。 解任を求めるには、「任務を怠った」こと、ある・・・