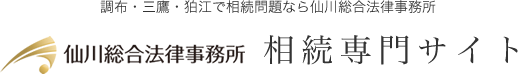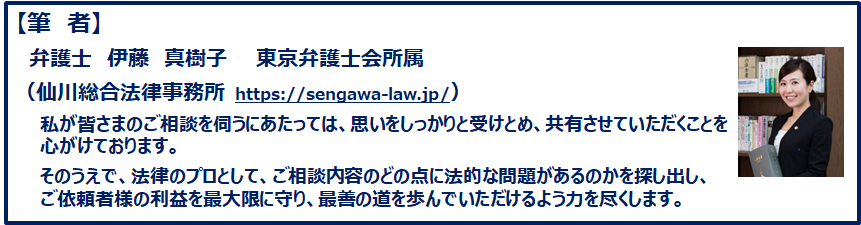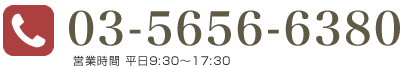相続コラム
遺言書
遺言書
自筆証書遺言に関する法改正について
2023.04.14
自筆証書遺言に関する法改正について、弁護士が解説します
1 自筆証書遺言の方式緩和~財産目録をパソコン等で作成できるように
<以前は全て手書きする必要があった>
旧法では、自筆証書遺言は、財産目録も含め全てを遺言者が手書きしなければならないとされていました。
そのため、相続財産の数や種類が多い場合など、遺言者の負担が大きく、また、誤字脱字が生じることによって遺言書が無効となるリスクがありました。
<目録をパソコン等で作成することが認められた>
上記のような問題点をクリアするため、民法の改正が行われ、新法においては、相続財産の目録部分をパソコンなどの自筆によらない方式で作成して添付することが認められました(民法968条2項前段)。
民法
(自筆証書遺言)第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
<目録として添付できる主なもの>
・パソコンで作成したリスト
・他人が代筆したもの
・預金通帳等のコピー
・不動産全部事項証明書
<注意点>
一枚の用紙に本文部分と目録部分を混在させることは認められないと考えられています。
例えば、通帳のコピーを使用する場合に、コピーの余白部分に遺言を自筆した場合、遺言書全体が無効となる可能性があります。
2 遺言書保管制度の創設
自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べ、費用がかからず、証人が不要など簡易に作成できるというメリットがあります。
他方で、遺言書の紛失や、相続人等による隠匿・変造のリスクがあるというデメリットがあります。
このような問題をクリアするため、法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。
<保管の手続き>
遺言者は、法務大臣の指定する法務局(以下「遺言書保管所」と言います。)に自ら出向いて遺言書の保管を申請する必要があります。
家族や知人などに頼んで申請することはできません。
また、保管できる遺言書は封がなされていない状態であることが必要です。
<申請の撤回や返還の方法>
遺言者が、申請した遺言書の保管申請を撤回するためには、自ら遺言書保管所に出向く必要があります。
そのため、病気などの事情により遺言者自らが遺言書保管所へ出頭できない場合は、保管申請の撤回や返還請求はできないことになるため注意が必要です。
<遺言書の変更方法>
遺言の内容を変更するためには、一度保管申請をした遺言書の申請を撤回したうえで、新たな遺言書を作成する必要があります。
<遺言者が死亡した後の取扱い>
◆ 自筆証書遺言は、通常、家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、遺言書保管所に保管されている関係遺言書については検認手続きは不要です。
◆ 関係遺言書についての有無の照会
遺言者が死亡した場合、誰でも、「関係遺言書」(請求者が相続人・受遺者等となっている遺言書)が、遺言書保管所に保管されているか否かを確認することができます。
◆ 関係遺言書の写し等の交付請求
相続人や受遺者等の関係者など、一定の人のみ、遺言書保管所に対し、関係遺言書の写し等を交付するよう請求することが可能です。
◆ 関係遺言書の原本の閲覧
相続人や受遺者等の関係者など、一定の人のみ、遺言書保管所に対し、関係遺言書の写し等を交付するよう請求することが可能です。
その他の関連コラム
遺言書
遺言の検認
2020.04.28
検認の意味や手続きについて 1 遺言の検認とは 公正証書による遺言ではない遺言書(自筆証書遺言など)がある場合、相続人の方は、遺言書を発見後遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないことが定・・・
遺言書
自筆証書遺言をみつけたが、どうしたらよいか~検認について~
2018.08.22
自筆証書遺言をみつけたが、どうしたらよいか~検認について~ 1 検認とは 自筆証書遺言書を補完していた人や、発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して調査を求めなければなりません。 これを検認・・・
遺言書
遺言書のメリット
2018.08.07
遺言書のメリット 1 なぜ遺言書を書くのか 相続に関してトラブルになってしまっている事案の法律相談を受けるなかで、「遺言書があればよかったんですが…。」と言うお話になることが多々あります。 例・・・
遺言書
公正証書遺言の作成方法
2020.02.05
公正証書遺言は作成方法や作成場所、作成の流れなど 1 公正証書遺言とは 公正証書遺言とは、遺言をする方が、公証人の前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言の内容を文章にまとめて作成する遺言書です・・・
遺言書
認知症の人は遺言書を作れるか
2018.08.17
認知症の人は遺言書を作れるか 1 認知症と遺言能力 遺言書を法的に有効に作成できる能力のことを遺言能力と言います。 この遺言能力は、自ら判断しその意思を表明する能力(意思能力)のある15歳以上の人であれば認・・・
遺言書
遺言書が複数残されていた場合
2018.08.29
遺言書が複数残されていた場合 1 遺言書が複数ある場合 被相続人が生前に「遺言書があるのでその通りにするように。」と常々言っていたところ、いざ被相続人が亡くなった後に自宅を整理してみたら、2通も3通も遺言書・・・
その他
遺言執行者の選任と役割
2018.08.23
遺言執行者の選任と役割 1 遺言執行者とは 亡くなった人の遺言が残されていた場合、その遺言の内容を実現するためには、様々な手続きが必要です。 預貯金の解約・分配手続きや、不動産の登記手続き、遺贈や寄附行為な・・・
遺言書
遺言書の書き方
2018.08.08
遺言書の書き方 1 遺言書の種類 法的に効力を認められる遺言書には、以下の通りいくつかの種類があります。 ① 自筆証書遺言 一人で作成することが出来る最も簡易な遺言書です。 ② 公正証書遺言 公・・・
遺言書
遺言書の探し方
2020.05.15
遺言書があるはずなのに見つからない場合、どうしたらよいか。 1 通常の保管方法 被相続人が、生前、公正証書遺言を作成したと言っていたものの、それがどこにあるかわからない場合、どうしたらよいでしょうか。 公正・・・